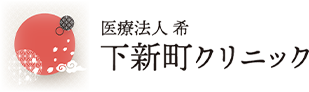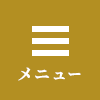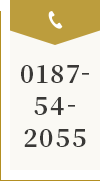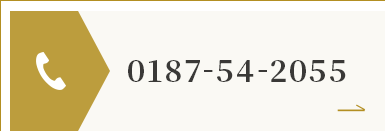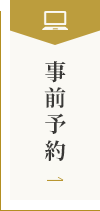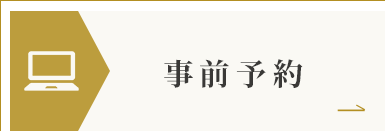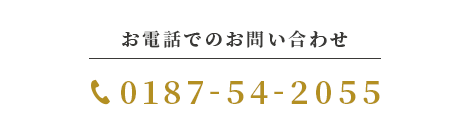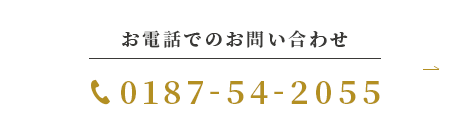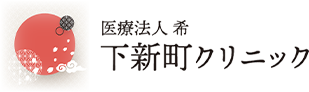インフルエンザ予防接種
インフルエンザとは
 インフルエンザウイルスを病原体とする急性の『肺と気道のウイルス感染症』です。例年、1月〜3月に大きな流行が見られます。
インフルエンザウイルスを病原体とする急性の『肺と気道のウイルス感染症』です。例年、1月〜3月に大きな流行が見られます。
感染すると、
- 発熱
- 鼻水
- のどの痛み
- せき
- 頭痛
- 筋肉痛、全身のだるさ(けん怠感)
などの症状が生じます。
予防接種のタイミング
例年11月下旬〜12月上旬にかけてインフルエンザは流行り始めるため、遅くても11月下旬〜12月上旬には予防接種を受けておくのが望ましいといえます。
予防接種可能な期間について
仙北市では10月に予定が確定し、ワクチン接種の予約ができるようになります。
予防接種ができない方
- 明らかに発熱のある人(一般的に、体温が37.5℃以上)
- 急性疾患に罹患中(かぜや急性胃腸炎で内服中など)
- ワクチンで発熱、アレルギー反応をおこしたことのある方
- 上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある方
肺炎球菌ワクチン予防接種
肺炎球菌ワクチンとは
 肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌が起因するさまざまな病気(感染症)を防ぐためのワクチンです。
肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌が起因するさまざまな病気(感染症)を防ぐためのワクチンです。
たとえば、肺炎はさまざまな種類の細菌やウイルスの感染によって引き起こしますが、その原因の第1位となっているのが肺炎球菌による細菌感染です。
肺炎球菌は多くの種類が存在し、このワクチンは1回の接種で多数の型に効くようにつくられています。
持ち物
- お知らせのハガキ
- 健康保険証(住所・年齢が確認できるもの)
- 身体障害者手帳 など
麻疹風疹ワクチン予防接種
麻疹風疹ワクチンとは
 麻疹(はしか)と風疹(ふうしん)とは、飛沫感染によって、人から人へ感染する感染力がとても強い感染症です。麻疹の場合は重症化して肺炎や脳炎などに至り死亡するリスクがあります。
麻疹(はしか)と風疹(ふうしん)とは、飛沫感染によって、人から人へ感染する感染力がとても強い感染症です。麻疹の場合は重症化して肺炎や脳炎などに至り死亡するリスクがあります。
抗体を持たないまたは低い抗体価の妊娠中の女性が妊娠20週頃までに風しんにかかると、赤ちゃんに耳が聞こえにくくなる、心臓に奇形が生じる、目が見えにくくなるなどの障がい(先天性風しん症候群)が現れる可能性があります。女性は、感染予防に必要な免疫を妊娠前に獲得しておくことが重要です。
妊娠中の女性は予防接種が受けられないため、抗体を持たないまたは低い抗体価の妊娠中の女性の周りにいる方は、風しんを発症しないように予防に努めてください。
麻疹と風疹は、事前にワクチンを接種することで病気を予防することができます。それぞれに対する免疫の有無は「抗体検査」によって調べることもできますので、一度ご相談ください。
対象ワクチン
- 麻疹風疹混合(MR)ワクチン
- 風疹単抗原ワクチン
おたふくかぜワクチン予防接種
おたふくかぜワクチンとは
 ムンプスウイルスに感染すると起こる「おたふくかぜ」は、「流行性耳下腺炎」または「ムンプス」とも呼ばれます。主として飛沫感染によって広がりますが、患者さんとの直接接触や、唾液を介した接触でも感染します。潜伏期は約2~3週間前後ですが、発症6日前ぐらいからウィルス排出があるので、自分でも気づかないうちに周囲に感染を広げていることがあります。
ムンプスウイルスに感染すると起こる「おたふくかぜ」は、「流行性耳下腺炎」または「ムンプス」とも呼ばれます。主として飛沫感染によって広がりますが、患者さんとの直接接触や、唾液を介した接触でも感染します。潜伏期は約2~3週間前後ですが、発症6日前ぐらいからウィルス排出があるので、自分でも気づかないうちに周囲に感染を広げていることがあります。
感染すると1週間程度続く耳下腺の腫脹、それに伴う高熱の症状が出ます。また、ムンプスウイルスは全身のいろいろな所(とくに神経組織や内分泌系腺組織)に広がるため注意が必要です。これにより様々な合併症(髄膜炎・脳炎、難聴、膵炎、精巣炎、卵巣炎 等)を起こしてきます。
対象者
- 1期:生後12か月から生後24か月に至るまでの乳幼児
- 2期:5歳以上7歳未満のお子さん
日本では、おたふくかぜワクチンの接種率は約40%と低い傾向にあるため、今後も大規模に流行してしまう可能性があります。
おたふくかぜにかかったことがある方以外の全ての人に、ワクチンの2回接種を推奨いたします。
帯状疱疹ワクチン
帯状疱疹ワクチンとは
 帯状疱疹の原因は水痘(すいとう)・帯状疱疹ウイルスです。日本の成人のおよそ9割はこのウイルスをもっていると言われ、加齢、疲労、ストレスなどで体の免疫力が低下すると、ウイルスが活動、増殖しはじめ、帯状疱疹になります。50歳以上になると発症率が高くなり、日本では80歳までに約3人に1人が帯状疱疹になると言われています。
帯状疱疹の原因は水痘(すいとう)・帯状疱疹ウイルスです。日本の成人のおよそ9割はこのウイルスをもっていると言われ、加齢、疲労、ストレスなどで体の免疫力が低下すると、ウイルスが活動、増殖しはじめ、帯状疱疹になります。50歳以上になると発症率が高くなり、日本では80歳までに約3人に1人が帯状疱疹になると言われています。
予防接種は帯状疱疹を完全に防ぐものではありませんが、接種をすると水痘・帯状疱疹ウイルスに対しての免疫力を高め、たとえ発症しても軽くすむという報告もあります。神経痛などの重症化を予防する意味もありますので、接種をお勧めします。
対象者
- 50歳以上の方
破傷風トキソイド
破傷風トキソイド(ワクチン)とは
 破傷風は破傷風菌が傷口から入ることで発症する感染症です。
破傷風は破傷風菌が傷口から入ることで発症する感染症です。
手足のしびれや引きつるなどの軽度の症状をはじめ、全身のけいれんや呼吸障害などを引き起こします。
破傷風は1968年から定期接種となっていますが、1967年以前に生まれた方はほとんどワクチンを受けておらず、発症率は高い傾向にあります。
山での作業中に深い傷を負うなどのケガをされた方が、破傷風にかかる場合があります。
また、ガーデニングなどでできる小さな傷でも発症することもありますので、ほぼ全ての方に接種するメリットがあります。
1968年以降に生まれた方は、追加接種となりますので三種混合ワクチンを使用します。
三種混合ワクチンは、百日せきやジフテリアの免疫力も同時に上げられるというメリットがあります。